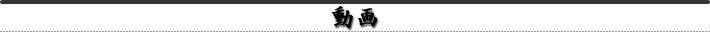4分割の山から4A出現の意外な歴史(2025.11.28up)
はじめに
セルフワーキングマジックが嫌いな私ですが、9月14日に32年ぶりの作品集”Super Self-Working Part 2”を発行しました。嫌いな内容で何故2回も本を発行するのかと問われそうですが、そのことに関しては本の「まえがき」に記載しました。出版記念パーテーも開催し、50名以上の多数の方に参加頂き盛大に終えることができました。「まえがき」には演じるのであれば、繰り返し操作を減らす、セットをなくす、もっと意外性のある結末にしなさいと好きなことを書いています。例となる12作品と私が影響を受けた奇術関係者20人についても掲載しました。作品の解説は簡潔にして、原理や歴史経過に重点をおいています。新たな作品作りの参考になることを願いました。
ところで、この本ではセットをなくすと書いていますが、最後の12作品目の「ピクニックエーセスの謎」では52枚全てをセットしています。原案は4分割の山のトップにエースが現れるだけの現象です。しかし、今回の作品ではその後も次の現象が起こり、最後には4つの山が各マークのA~Kにそろいます。これを掲載したのは、セット状態を覚える必要がないことが分かったからです。「ピクニックエーセス」の歴史についてだけは報告しましたが、4分割の山から4A出現に関する全体の歴史までは掲載できませんでした。このコラムでは、その点に重点をおいて報告することにしました。簡単にまとめ終わると思っていたのは大きな間違いで、次々と意外なことが明らかになり、まとめるのが大変でした。エドワード・マルローが関わると、毎回、そのようになってしまうのが厄介でもあり面白い点でもあります。
デックを4分割してトップからエース出現の全体像
客が4分割するか、演者が4分割するか。分割した山のトップを客が表向けるか演者が表向けるか。分割した後でちょっとした操作が必要かなどでタイプが分かれます。演者が分割する場合に直ぐ思い浮かぶのが、スリップカットを繰り返す方法です。かなり昔からあると思っていたのですが、最初の解説が1948年の「ターベルコース第5巻」でした。意外であったのが、それよりも前に発表されていたのが、4分割を客にさせるセルフワーキングによる方法でした。1939年にはBelchouの方法が発表され、その後「ポーカープレイヤーズピクニック」や「エース・ボナンザ」の名前でよく知られるようになります。なお、このような方法はBelchouが最初ではなく、その数年前には別のセルフワーキング2作品が発表されていることも分かりました。
1956年から57年に重要な3つのタイプが誕生しますが、1964年までほとんど地下にもぐったままで一般のマニアには知られていませんでした。2つのタイプはマルローや一部のマニアの間で知られていた程度で、残り1つはマイナーなレクチャノートに掲載されていたのが理由です。1番目の方法は、演者の左手に持ったデックから、客に4分の1づつ取らせる方法です。1956年12月のBob Veeserとマルローとの手紙のやりとりから始まり、”The Spectator Cuts the Aces”の名前でマルローがかなりの数の方法を考案しているようですが、ほとんど発表されていません。研究分野としては面白いのですが、実践で使えるものが少ないのだと思います。文献に初めて登場するのは1964年のマルローのファローシャフルの本です。ファローシャフルを使うだけでもマニアックさが伝わってきます。実践的になるのは1985年のRandy Wakemanの方法や、その後のJohn Bannonの方法が登場してからです。
2番目のタイプは、4分割された山のトップカードを演者が素早く表向けて示すものです。エースは1つの山の上に4枚ある状態か、2つの山に2枚づつある状態から行い、各山の上のエースを表向けたように見せる方法です。1956年のFrancis Haxtonが最初で、最終案とも言える優れた方法が1990年発表の高木重朗氏の方法と言えます。3番目のタイプが、4分割の山の上から1枚づつ取って重ね、それらを表向けて各山の上へ戻す方法です。最初の考案は1957年のNeal Eliasですが未発表のままでした。この関連作品が初めて文献に登場するのは1964年12月のGenii誌で、ラリー・ジェニングスの「リーピング・エーセス」のタイトルになっています。これは独自の考案かEliasの影響があるのかは分かりません。この登場にマルローが焦ったようで、その直ぐ後でこのタイプの改案を次々に発表しています。歴史を調べますと、進化状態だけでなく、意外なことがいろいろと分かりました。まずは、演者自身が4分割してAを出現させる作品から報告させて頂きます。
演者自身が4分割して4Aを出現させる作品
すぐに思いうかぶのが、ヒンズーシャフルを行う状態でデックを持ち、トップカードとボトムの4分の1をカットしてテーブルへ置くスリップカットの方法です。これを繰り返して4つの山を作り、トップからエースを現すことができます。テーブルに置いて行うのであれば、リフルシャフルを行うようにデックを横向きにしてスリップカットする方法が考えられます。海外の古い文献でそのような解説を探しましたがなかなか見つかりません。やっと、見つかったのが1948年の「ターベルコース第5巻」の「バーンハードの4Aオープナー」です。テーブルにデックを横向きに置く方法です。また、1973年のハリー・ロレイン著”Rim Shots”にも”Halo Again”が解説されています。Haloとはハリー・ロレインのことで、彼のボトム・スリップカットを使う方法です。かなり以前にハリー・ロレインのレクチャーを受けたことがありますが、いろいろ行われた中で”Halo Again”の印象だけが残っています。テンポよく4分割されていたのが気持ちよかったのだと思います。トップに4Aをセットして、表向きのオーバーハンドシャフルする状態でスリップカットを使い、各パケットを裏向けてテーブルへ置いていました。
もっとテンポよく4分割してテンポよく各山のエースを表向ける作品が、1970年代後半より知られるようになります。1978年のAl Smithの方法では、エースをトップに2枚、中央に2枚を持ってきて、両手を使って素早く4分割し、すぐに左右の手にある山のトップのエース1枚づつを持ち上げて表向けます。この2枚を何気なく別の2つの山へ置き、その後、残りの2枚のエースも表向けて、それらはその山の上へ置くことになります。4つの山を四角形状に配置し、両手が交差する動きをうまく使っていました。1980年にフランク・ガルシアの本に解説されたFather Cyprianの方法では、4枚のエースをデックの中へバラバラに入れる操作から開始しています。この方法では両手の交差はありません。1990年のガリ・オレットの方法では、デックのトップに4枚のエースがある状態から、素早く4分割して、各山の上にエースを表向けていました。両手の交差もうまく取り入れています。そして、この分野の最終形といってもよい方法が、1990年に高木重朗氏により発表されます。客に4分割させているのが特徴です。デックのトップに4枚のエースがある状態で分割させて、両手の交差をうまく使ってエースを出現させていました。
ところで、このタイプの驚きの発見が、早い年数の1976年にはポール・ハリスが意外な現象の作品として発表されていたことです。演者の左手に持っているデックから最初の4分の1は演者が分割しますが、残りは客に分割させて4つの山にしています。2つの山にはAが2枚づつある状態で演じていました。それだけでなく、4つ山の下から銀貨が出現します。うまくエースの場所で分割できたので、ギャンブルでも稼ぐことができる演出です。さらに、もっと早い段階で発表されていた作品の存在も分かりました。ネット上で歴史を調べますと、1956年のFrancis Haxtonのレクチャーノートに、これらの元になる方法が既に解説されていたことが分かりました。また、1969年10月のThe Linking Ring誌にはIan Baxterの方法も解説されているそうです。残念ですが、それらの方法の詳細は分かりません。
最初に発表されていたセルフワーキングによる数作品
1940年発行の”Expert Card Technique”は素晴らしい本です。当時の最先端の技術やカード奇術が解説されているからです。しかし、掲載方法に多数の問題がありました。考案者の許可を取らずに勝手に解説し、しかも少し内容を変えていました。今回のテーマと関わりがある「エース・アセンブリー」のタイトルの作品では、タイトルの付け方に問題を感じました。エースが1箇所に集まるのではなく、4分割の山の上に現れるのに「エース・アセンブリー」の名前にしていたからです。これには古い方法と新しい方法の2つが解説されています。新しい方法が1939年のBelchouの方法ですが、少しだけ方法を変えて解説しています。古い方法は、古いと言ってもBelchouと同じ1939年に発表されたMoorhouseの方法が元になっているようです。その解説の中で20年前から行っていたと書かれていました。なお、1935年のルーファス・スティール編集のカードマジックの本にもCaryl Flemingの同様な方法が解説されています。これらの3つの古い方法には違いがありますが、各山のトップ部分だけの移動である共通点があります。Moorhouseはランダムに見える5回の移動、Flemingは山の半分や2枚も含む5回の移動、Expert Cardの本はランダムな1枚づつの7回の移動になっています。いずれにしても覚えにくい方法です。Belchouの方法では、3枚をテーブルへ配り、1枚づつ他の山の上へ配っています。シンプルで覚えやすい利点があり、その後の主流になります。Belchouの方法が1948年の「ロイヤルロード」の本で「ポーカープレイヤーズピクニック」の名前で解説され、ボトムに3枚づつ回す方法に変わっていました。セリフや演出に重点をおいた解説が参考になります。1968年のTemple C. Pattonの本では「エース・ボナンザ」の名前で、4分割の山を四角形に配置して演じられます。高木重朗氏や宮中桂煥氏の本では、こちらの方法を採用して解説されていました。
"The Spectator Cuts the Aces”の歴史
”The Spectator Cuts the Aces”のタイトルやそれを少し変えたタイトルで次々と作品を発表し、名前を定着させたのはエドワード・マルローです。1965年の段階で45番目の方法を解説しています。始まりは1956年12月で、この考えと数作品をBob Veeserがマルローへ手紙で送ったことが元になります。しかし、文献に初めて登場するのはかなり後で、1964年のマルロー著”Faro Controlled Miracles”が最初です。この現象に関連した数作品が解説されていますが、思っていた印象と違うものばかりでした。プロブレムとして考えるのは面白くても、演じる気にはなれないものばかりです。ファローシャフルやオーバーハンドシャフルを使ってAを特定の位置へコントロールすることに解説の重点をおいています。4分割した後もすぐにエースを表向けることができません。これらに比べると同年の12月に発表されたGenii誌のラリー・ジェニングスの「リーピング・エーセス」の方がシンプルで実践的です。4つの山のトップから1枚づつを取って重ね、その後で1枚づつ表向けて各山の上へ戻す方法です。こちらの方が現在ではよく知られている印象です。
このジェニングの発表から3ヶ月後の”The New Tops” (1965年3月)では、マルローが”A Problem Posed”「提起されたプロブレム」を発表しています。1956年12月のBob Veeserの手紙の事から1964年までの歴史経過に興味がひきつけられます。これまでのプライベートノートや発表作品を加えて34作品になると報告していました。そして、ここでは35番目の方法から41番までと45番目の方法が解説されます。その35番目と36番目の作品は、1964年のジェニングスの方法に似ています。Aをデックのボトムに3枚とトップに1枚がある状態にして、客に4分割させていたからです。ボトムに3Aがある山を左手で持つ点も同じです。その後の操作が違っており、マルローの方法も悪くありません。興味深いことが、これを記録したのが1964年3月としていた点です。ジェニングスの発表がその後の12月ですので、ジェニングスの方法を読んで改案したのではないと言いたいのでしょうか。それでは、ジェニングスがマルローの方法の情報を得て改案したのかと言えば、それも違います。ジェニングスも考案年数を書いており、1961年となっていたからです。
マルローの歴史報告には、1957年4月にNeal Eliasによる別の解決法”Spectator Cuts the Aces Plus”があると書いていますが、その内容の記載がありません。それから大きく年数が経過した1975年の”The Hierophant 7”になって、やっと、Neal Eliasの1957年の方法が解説されます。それはデックのトップに4Aがある状態にして客に4分割させ、各山のトップカードを左手の上へ重ねる方法です。その後、1枚づつエースを表向けて各山へ戻しています。その解説の後でマルローの4つの改案も掲載しています。1965年の段階で、各山から1枚づつ取る方法を発表しているのに、マルローはNeal Eliasの作品が元になっていると何故書かなかったのかが不可解です。
1枚づつ取った後で各山へ戻す方法のその後の変化
1957年考案のNeal Eliasの方法が1975年の”The Hierophant 7”で解説されます。左手の上へ直接1枚づつ重ねて置く方法でした。その後の主流になる1つの山を取り上げて左手へ置く方法ではありません。1つの山の上に4枚のエースがあり、その4枚は手前エンドにブリッジがかけられています。関連作品の最初の登場が1964年12月のジェニングスで、デックのボトムに3枚、トップに1枚のエースがある状態で4分割されます。そして、ボトムに3Aがある山を左手の上へ置く方法です。1965年3月にはマルローが多数の方法を解説しますが、最もシンプルなのが”37th Method”の方法でした。デックのトップに4Aがある状態で4分割させ、4Aがある山を左手に置いて演じています。37thはマルローのこの関連作品全ての番号で、今回の方法では3番目になります。その後、1969年アルトン・シャープ、1971年ハリー・ロレイン、1972年ジム・サプライズの改案が発表されます。そして、日本では1976年にフランク・ガルシアの方法が解説されます。これは1976年のFISMでガルシアより教わった方法を高木重朗氏が日本で解説されたものです。海外ではたぶん発表されていない可能性があります。これまでに発表された作品と大きな違いがありませんが、シンプルな点がよいのだと思います。マルローはマルローマガジンVol.3やVol.5にも多数の作品が掲載されますが、全てが客にデックをシャフルさせた後で4分割させています。つまり、エースは4分割させた後で膝などの別のところから加える方法になります。さまざまな方法が解説されます。1979年のVol.3では3作品、1984年のVol.5では12作品もありました。
客が4分割して、客によりAを表向けさせる方法の出現
マルローは”Spectator Cuts to and Turns The Aces”の少し長いタイトルで発表しています。4分割後に各山のエースを表向けるのも客が行います。この最初となるのが、上記でも報告したセルフワーキングによる方法です。全てを演者の指示で客が行いますが、分割した後でだらだらした操作が必要となる問題がありました。客の4分割後、直ぐに客がエースを表向けるのが理想ですが、かなり大変だと思ってしまいます。実を言えば、マルローが最初に考案した方法を少し改良すれば可能なことでしたが、その当時はそこまで考えていなかったのかもしれません。1956年12月にBob Veeserの提案で考案したマルローの方法が1978年の”The New Tops” Vol.16 No.7で初めて解説されます。デックのトップとボトムにエースが2枚づつある状態で演者の左手に持ち、上部から客に4分の1づつ取らせる方法です。トップパーム、ボトムスティール、ボトムディールを使うので大変ですがシンプルな方法です。しかし、ボトムディールには問題を感じました。その部分の改案も、その直ぐ後の別法で解説されていますが、まだまだ問題がありました。
マルローが客にエースを表向けさせることに意識をもって発表したのが1975年の”The Hierophant 7”です。1957年のNeal Eliasの各山のトップのカードを集めて各山に戻す方法解説の後で、客に表向けさせるマルローの改案を発表しています。各山のトップカードを集めた後で「あ!忘れていました」と言って裏向きのまま各山に戻す方法です。そして、山の上のカードを客にひっくり返させています。実践的で面白い考えですが、使いたくない方法です。これ以外に3つの方法が解説されます。やはり、スマートな方法で演じるには左手に持った状態から客に4分割させるのが最適なようです。1985年のRandy Wakemanが、1956年のマルローの方法に比べてかなり楽な方法で解説しています。それでもボトム・スティールだけは必要でした。その後、その部分をジョン・バノンが楽な方法に改案しています。日本語の本では富山達也訳「ジョン・バノン・カードマジック」の”Final Verdict”が大いに参考になります。
おわりに
おわりに) 今回はこのテーマの全体を調べ直すよい機会になりました。やはり、予想以上にマルローが多数の作品を考案し発表されていました。未発表を含めると100は超えていると思います。しかし、実演で使いたくなるのは1作品か2作品だと思います。マルローの場合、実用的でない作品でもそれぞれに面白い発想があり、目が離せないのがマルローの素晴らしさです。今回のテーマの作品では日本で解説されているのは多くありません。しかし、それらは実戦で使えるものばかりです。セルフワーキングでは「ポーカープレイヤーズピクニック」や「エース・ボナンザ」と呼ばれるBelchou原案の作品。全ての山のトップを表向けたように見せる方法では高木重朗氏の方法。各山から1枚づつ集める方法では、ジェニングス、マルロー(37番目の方法)、ガルシアの方法。左手のデックから客に4分割させるのはジョン・バノンの方法が解説されています。それらが掲載された本は下記の参考文献を参考にして下さい。なお、このテーマの発表文献が多数ありますので、ここでは今回報告しました作品を中心に参考文献として掲載しました。
参考文献
1935 W.F.Rufus Steele Card Tricks That Are Easy to Learn Easy to Do
Caryl Fleming The Four-Ace Merry Mix Up
1939 Frederick Moorhouse Goldston’s Magical Quarterty
Vol.5 No.2 March 407ページ The Return of the Aces
1939 Oscar Weigle Dragon誌 6月号 作品名不明 Steve Belchou 原案
1940 Hugard & Braue Expert Card Technique Ace Assembly
The Old Method
The New Method 上記のBelchouの方法を少し変更
1948 Hugard & Braue The Royal Road to Card Magic
A Poker Player’s Picnic 上記の1939年の方法を少し変更
1948 Barnhardt The Tarbell Course in Magic Vol.5 Four Ace Opener
1956 Francis Haxton An English Trip (Lecture Notes)
1964 Edward Marlo Faro Controlled Miracles
Bob Veeser A Subtlety for The Spectator Cuts the Aces
Edward Marlo Marlo’s Four Card Miracle
Acetimation Veeser、Simon、Marlo 3人の方法
1964 Larry Jennings Genii 12月 Reaping Aces(1961年考案)
1965 Edward Marlo The New Tops March A Problem Posed
1956年からの歴史 1964年の35~41と45番目の方法
1968 Temple C. Patton Card Tricks Anybody Can Do Ace Bonanza
1969 Alton Sharpe Expert Card Mysteries Jumping Jacks
1969 Ian Baxter The Linking Ring 10月
1971 Harry Lorayne Reputation Makers To Catch an Ace 7作品
1972 Jim Surprise Card Cavalcade 1 Surprise Aces
1973 Harry Lorayne Rim Shots Halo Again
1974 Edward Marlo The Unexpected Card Book
Another Spectator Cuts the Aces (1971)
1975 Neal Elias The Hierophant 7 Spectator Cuts the Aces Plus(1957年)
1975 Edward Marlo The Hierophant 7
Spectator Cuts to and Turns The Aces Method 1~4
1976 Edward Marlo The New Tops Vol.16 No.7
Spectator Cuts the Aces Method 1~4 (1956.12.29)
1976 Edward Marlo The New Tops Vol.16 No.8&9
Spectator Cuts Aces Method 1~7 (1957.12.12)
1976 Edward Marlo Kabbala Vol.3 No.9
The Spectator Cuts To And Turns Over The Aces (1968)
1976 Frank Garcia 奇術界報 419号 ブラフ・エース・オープナー
FISMウィーン大会にて(高木重朗解説)
1976 Paul Harris The Magic of Paul Harris Silver and Aces
1978 Al Smith The Talon 2 Cross Over Aces
1979 Edward Marlo Marlo’s Magazine Vol.3 Spectator Cuts Aces 3作品
1979 Harry Lorayne Quantum Leaps Double Take
1980 The Elegant Card Magic of Father Cyprian Swindle Cut Aces
1983 高木重朗(編) カードマジック事典 Aの出現
エース・ボナンザ ジェニングスのリーピングエーセス
1984 Edward Marlo Marlo’s Magazine Vol.5 Spectator’s Ace Cutting 12作品
1985 Randy Wakeman Formula One Close Up
The Spectator Cuts To And Turns Over The Aces
1986 Edward Marlo Thirty Five Years Later Another Spectator Cuts The Aces
1989 Edward Marlo So Soon? Spectator Cuts Aces to Face
1990 高木重朗 The Amazing Miracles of Shigeo Takagi Who Cuts First?
1990 Gary Ouellet Close Up Illusions Three Second Wonder
1991 John Bannon Smoke and Mirrors Directed Verdict
2004 John Bannon Dear Mr. Fantasy Final Verdict
2013 上記日本語版 ジョン・バノン・カードマジック 富山達也訳
2015 宮中桂煥 図解 カードマジック大事典 4Aオープナー
エース・ボナンザ / ガルシア / マルロー / ジェニングス
2021 Jon Racherbaumer Picnic- Pocus Polishing “Poker Player’s Picnic”