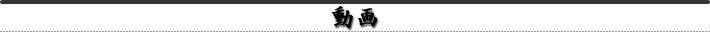カードの非対称交換現象の面白さ(2025.07.23up)
はじめに
前回のコラムから4ヶ月が経過していました。最近の2ヶ月は、9月発行の私の作品集「スーパーセルフワーキング・パート 2」の原稿に集中していました。やっと書き終わり、すぐにコラム原稿に方向転換し、取り上げたくなったテーマが技法使用の非対称交換現象(アシンメトリック・トランスポジション)です。単にカードが入れ替わるだけでなく枚数も変わります。コインで言えば、銀貨が銅貨とチャイナに入れ替わるような現象です。私がマニア相手に挨拶がわりに演じるのがA~5を使う非対称交換現象です。偶数の2と4をテーブルへ置いたのに、奇数の1と3と5の3枚になり、手元に残っているのが2と4のカードになります。マニアに知られているダブルリフトのような技法を使ったのではマニアには通用しません。1993年の「スーパーセルフワーキング」の本の冒頭に解説しました。セルフワーキングではないけれども、最も演じることが多いマジックとして掲載しました。その後、完全にマニアを煙に巻くマジックへと改良を加えています。この現象を全く違う発想で解決されていたのが佐藤大輔さんです。独自の方法による頭の良さに感心させられます。2024年12月発行の彼の著書”Exit Strategy”に解説されました。64ページのハードカバーの本で10作品が掲載されています。いずれの作品も現象や方法の発想が素晴らしく、技法の使い方にも多くの刺激を受けました。
”Exit Strategy”の本を少し紹介させて頂きますと、最初の作品では、客が3分割したトップの3枚の合計枚数目から客のカードが出現します。これまでになかった発想に感心させられます。また、デックのトップとボトムから2枚づつ取り出し続けてストップをかけてもらうと、この2枚の色と数が、先に出していた2枚と一致します。ありそうでなかったシンプルで興味がわく現象です。カードケースの内側と外側のカードが入れ替わる現象は、イリュージョンのカード版の印象です。その後、この2枚が客のカードを見つけ出し、ケースの中に入ってサンドイッチします。「混ざるカード」や”Follow the Leader”も独特の技法センスで演じられています。「ロイヤル・マリッジ」の現象や、客と演者のカードのスペリング・トリックも独特です。この本の最後の作品だけは少し仕掛けが必要です。1枚のブランクフェイスカードの裏に客が全く自由に思ったカードの名前を書いて封筒に入れ、その客にプレゼントします。もちろん、想像通りの現象が起こります。著者がある女性のお別れ会で実際に演じたメッセージ性のある作品です。著書全体のイメージがシンプルでありながらオシャレです。本の最後に各作品のコメントが7ページかけて書かれていたのも価値を高めています。佐藤大輔さんは英国のロイ・ウォルトンに会われた数少ない日本人です。また、マニア度の高い英国の鬼才Jerry Sadowitzとも交流されていたことが奇跡的と言えます。英国留学中でのことです。2014年4月に開催された箱根クロースアップ祭にスペインのタマリッツがゲスト出演されました。タマリッツが2日間の演技を見た日本人の中から一人を選んで、スペインのタマリッツの有名な催しに招待されることになりました。それに選ばれてスペインへ行かれたのが佐藤さんでした。同じ名字の佐藤喜義さんの”The Amazing Sally”の3冊や、最近では2021年にピーター・ケーンの翻訳本を発行されています。そして、やっと、ご本人の著書が発行されました。素敵な本でしたので紹介が少し長くなりました。それでは、本題に入ることにします。
非対称交換現象の歴史経過
カードを使ったこのような作品が、1970年代中頃から次々と発表されます。カード以外では、このような現象がかなり以前から演じられていたようですが、最初が何になるのかは調査ができていません。カードの現象でよく知られているのがホテル・ミステリーです。女性カードとしての2枚のQと4枚の男性としてのカードを使用したストーリー性のある作品です。完全な入れ替わり現象ではなく、3枚と3枚が2枚と4枚に変化します。「ホテル・ミステリー」以外では、1975年にはロイ・ウォルトンが1枚のジョーカーと4枚のQの入れ替わり現象を発表しています。”Card Cavalcade 3”に解説された”Runaround”ですが、トリプルクライマックスのラストに使われていました。入れ替わり現象だけで発表していたのが、1977年のポール・ハリスの「スーパー・マジック」の本に解説された「ダブル・モンテ」です。1枚と2枚が入れ替わるシンプルで面白いと思いましたが、方法が単純すぎて物足りなさがありました。そして、面白い現象に出会えたのが1990年のフィル・ゴールドステインの”Focus”に解説の”Budkin”です。冒頭で報告しました5枚使用の偶数2枚と奇数3枚の入れ替わり現象です。原案では何度もダブルリフトを繰り返す問題があり、それを減らすように工夫していると、全くダブルリフトを使わない方法が完成しました。それが私の挨拶がわりの作品となりました。このような現象に興味を持ち、上記のウォルトンの”Runaround”の1枚と4枚の入れ替わりや、ポール・ハリスの「ダブル・モンテ」もマニアに通用する方法を考えました。非対称交換現象のおかげで独自の方法を考える楽しみが加わりました。
ホテル・ミステリーについて
ホテルで起こる成人向け物語の不思議なトリックです。Qを女性、KやJや数のカードを男性としています。2つの部屋にQが1枚づつ入り、その後、各部屋に男性カードが2枚づつ入ります。ところが、各部屋を見ると一方は2枚のQ、他方は4枚の男性カードとなります。原案は1940年のヘンリー・クライストの”Aces and Kings”とされていますが、4枚づつの中での変化現象だけです。枚数の変化がありません。1942年にマルローが「ホテル・ミステリー」の名前をつけて4Qと4Kを使いましたが、枚数の変化はありません。枚数も変化するように変えたのは、1967年頃のパーシ・ダイアコニスが最初とされています。ダイアコニスについては、2014年フレンチドロップ・コラムの第65回に詳しく報告していますので、是非、読まれることをお勧めします。1959年頃に14歳であったダイアコニスは、ダイ・バーノンと2年間ほど一緒に旅に出て生活を共にし、その後、大学教授になる、ありえない経歴の人物です。なお、ダイアコニスの「ホテル・ミステリー」は発表されていませんが、そのことやそれを応用したマルローの数作品が1976年の「マルローマガジン第1巻」に解説されています。しかし、その前の1974年にはニック・トロストがThe New Tops誌に、また、1975年にはピーター・ケーンが作品集に違う物語で発表していました。私がこのマジックの存在を知るのは1976年発行のHarvey Rosenthalの”Close-up Sampler Part 2”での解説です。その作品よりも私が興味を持ったのは、1979年の英国の”The Talon No.4”に解説のJeff Busbyの物語です。現象が2回繰り返され、ホテルの探偵役のカードがフラストレーションを起こして2枚のQと一緒の部屋で、ムチを持った服装になる、かなりアダルトな物語です。そのムチを持った姿がタリホーのジョーカーであり、その面白さで一時期演じたこともありますが、すぐに演じなくなりました。私向きではないからです。私が気に入った方法が宮中桂煥氏の作品でした。たしか1990年頃に見せてもらった記憶があるのですが、それが解説されるのは2015年の「図解カードマジック大事典」が最初になるようです。その後、これまでとは少し違ったタイプのホテル・ミステリーが発表されます。1996年の「ラビリンス3号」に解説されたゆうきとも氏の「宿屋の怪」です。2枚のQの部屋に1枚の男性カードが入りますが、その部屋には同じ考えの男性カード4枚となり、2枚のQは別の部屋に移っている現象です。こちらの方法に私の興味がひきつけられ、これもダブルリフトや既存の方法を使わない作品を考えたくなります。そして、完成した作品を1998年の「RRMC レクチャーノート 3」に発表しました。これも私の好きな作品となり、私の挨拶がわりマジックNo.2となります。
おわりに
コラムとして実は別の予定していたテーマがあったのですが、9月発行予定の本の原稿作業のために十分な調査ができていませんでした。そこで、すぐにまとめることができるテーマとして非対称交換現象を取り上げました。最近発行された佐藤大輔さんの著書”Exit Strategy”の中の”Even Odds”の作品を読んで、このテーマでまとめたくなりました。以前にも調べていたこともあり、まとめやすいテーマでした。9月発行予定の私の本の原稿を書いていて思ったのは、本の制作のたいへんさです。本の内容だけでなく、本全体のセンスも関係してくるからです。その意味でも佐藤大輔さんの”Exit Strategy”は素晴らしい著書だと思い、少し長いコメントになりました。今回の中で報告しました私の挨拶がわりの2作品は、何の準備もなく、カードがあればいつでも演じられますので、機会があれば見て頂ければと思います。最後に参考文献ですが、ホテル・ミステリーに関しての作品数が多いので、ここでは今回のコラムに引用した作品だけの掲載としました。
参考文献
1974 Nick Trost The New Tops Vol.14 No.6 The Hotel Mystery Updated
1975 Roy Walton Card Cavalcade 3 Runaround
1975 Peter Kane A Further Sesson with Peter Kane The Diamond Robbery
1976 Edward Marlo Marlo magazine Vol.1 Motel Mystery
1976 Harvey Rosenthal Close-up Sampler Part 2 On The Hotel Trick
1977 Paul Harris Super Magic Double Monte
1979 Jeff Busby The Talon No.4 The Repeat Hotel Mystery
1990 Phil Goldstein Focus Budkin
2005年にTon 小野坂訳「パケット・トリック」として発行
1993 石田隆信 Super Self-Working ファイブ・カード・ミラクル
1996 Jon Racherbaumer The Looking Glass Winter 数名の作品
1996 高橋知之(ゆうきとも) ラビリンス 3号 宿屋の怪
1998 石田隆信 RRMC Lecture Notes 3 R. R. ホテル・ミステリー
2015 宮中桂煥 図解カードマジック大事典 ホテル・ミステリー
2024 佐藤大輔 Exit Strategy Even Odds